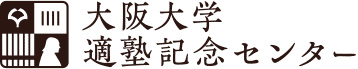活動日誌
2013年1月13日(日)中之島センター佐治敬三メモリアルホールにて、適塾記念センターシンポジウム「「鎖国」のベールの裏側で~ケンペルとその時代の日欧交流にせまる」が開催されました。
本シンポジウムはオランダ学研究部門発足を記念し、同研究部門が企画したものです。
当日は約180名にご参加いただきました。
講演1「ケンペルの来たころ―元禄期の出島・長崎・日本ー」
松井洋子教授(東京大学史料編纂所)
講演2「ケンペルが見た日本、ヨーロッパが見た日本」
中直一教授(言語文化研究科)
講演3「肥前窯業史におけるオランダ貿易の位置づけ」
野上健紀氏(佐賀県有田町歴史民俗資料館主査)
3名の専門家による講演のあと、講演者とファリシテーター・古谷大輔准教授(言語文化研究科、適塾記念センター兼任)による鼎談とが行われ、江戸時代の日本とヨーロッパとの交流の歴史について、様々な角度から考察されました。

古谷准教授、松井教授、中教授、野上主査による鼎談の様子
(朝日新聞社提供)
11月28日(水)18:00~20:00、中之島センター佐治敬三メモリアルホールにて適塾記念講演会が開催されました。
今回は適塾記念センター オランダ学研究部門の企画による講演会が行われました。

平野総長からの挨拶
【講演1】「新蘭学事始~今、オランダに学ぶこと」
松野明久教授(国際公共政策研究科)
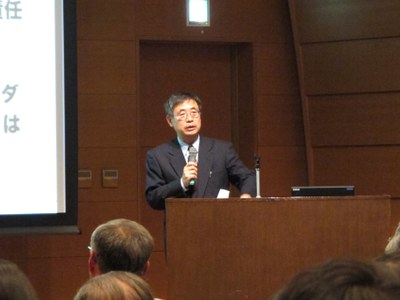
【講演2】「シーボルト・コレクションの歴史的意義と適塾の役割」
塚原東吾教授(神戸大学大学院国際文化学研究科)

現代のオランダ社会から日本は何を学ぶべきか、また、シーボルトの標本採集が日本の学者に与えた影響や母国での様子など、江戸時代から現代へと繋がるオランダと日本との交流について、多くを学べる場となりました。
11月5日(月)から11月22日(木)にかけて、阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット「公開講座フェスタ2012」が開催されました。
適塾記念会も同フェスタに参加しており、澤井実教授による講義「戦中戦後日本の研究開発」(11月7日(水)19:00~20:30)が行われました。講座では、戦時中の科学技術が継承される過程を詳細に解説され、今日のナショナル・イノベーション・システムについても言及されました。

講義を行う澤井教授
10月28日(日)今年度2回目の適塾見学会が開催され、10名の方にご参加いただきました。
「大坂の「舎密学(せいみがく)」」をテーマに、福田舞子特任研究員の案内で大阪舎密局跡や大阪城焔硝蔵などを見学。
近代の大阪が化学の最先端地域であった様子や、明治以後の適塾生たち業績の一部が紹介されました。

大村益次郎卿殉難報国之碑の前にて
9月15日、29日、10月13日(いずれも土曜日)の3回にわたり、第5回適塾講座が中之島センターにおいて開催されました。
今回の共通テーマは「黎明期日本医学の中心・適塾と近代大阪の疾病」です。
9月15日(土)14:00~15:30
「都市の若者と医学教育―適塾を国際的にみる」
鈴木晃仁教授(慶應義塾大学経済学部)
9月29日(土)
「Hygieneと衛生―長与専斎のみた欧米と日本」
永島剛准教授(専修大学経済学部)
10月13日(土)
「日本の工業化・都市化・結核」
花島誠人主任研究員(財団法人地域開発研究所)
友部謙一教授(経済学研究科)
適塾の担った役割、都市の疾病や衛生問題など、各専門家による充実した講義が行われ、各回約20名の方に参加いただきました。

鈴木教授による講座の様子